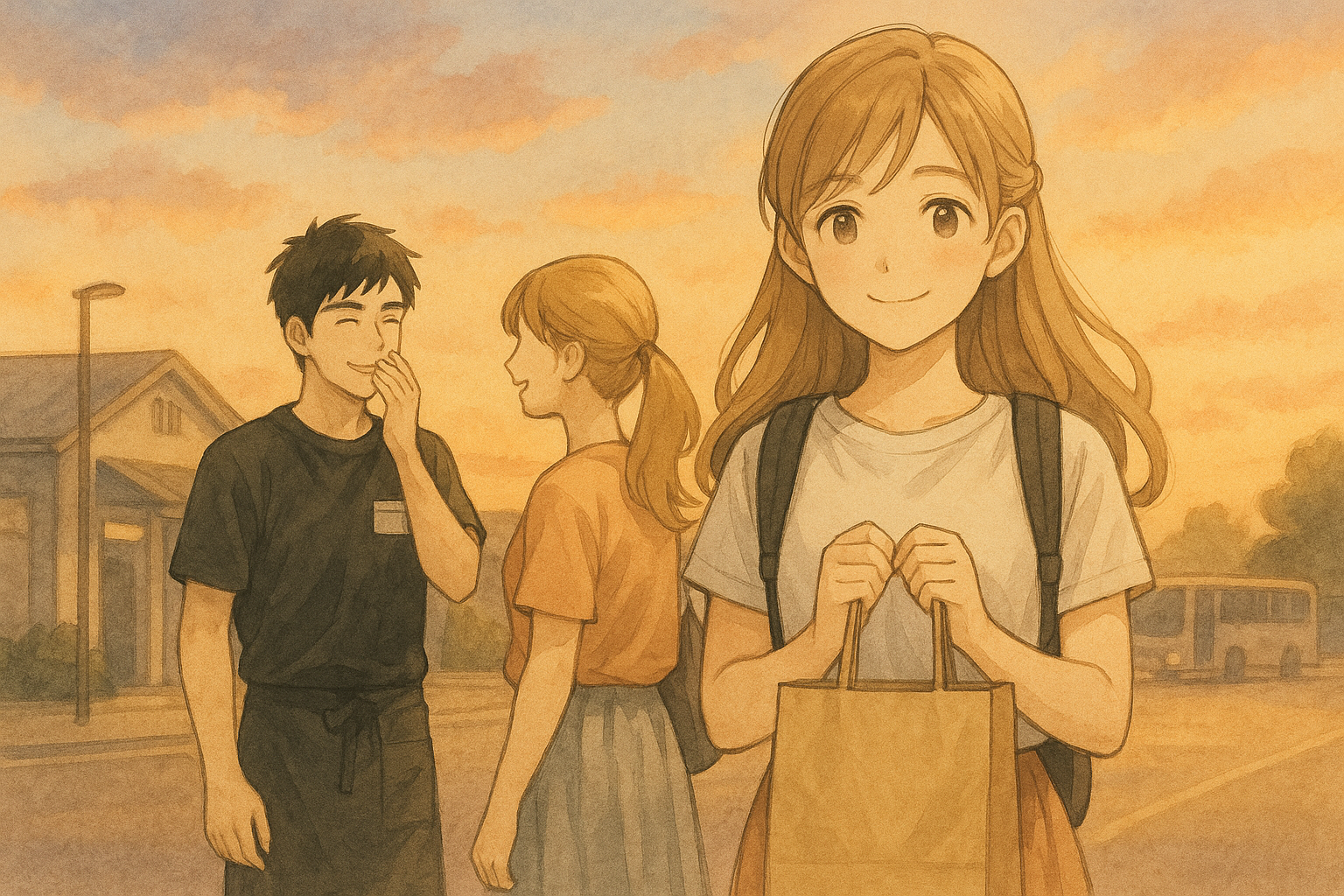休日の午後、手のひらに揺れるおみやげ
「あ、そうだ。ハルキにこれ、渡さなきゃ。」
こいこと。ヤングチーム鎌倉ドライブの余韻がまだ少し残る平日の午後。
アカリは自分の部屋のテーブルに置いていた小さな紙袋を手に取った。中には、江ノ島の雑貨屋で見つけたイルカのキーホルダー。ドライブに来られなかったハルキに、ほんの少しでも旅の空気を届けたくて買ったものだった。
「別にいらないって言われそうだけど……」
小さくつぶやいてから、スマホを手に取ってLINEを開く。
『今ヒマ? ドライブのおみやげ渡したいんだけど〜』
既読がすぐにつき、「今バイト終わったとこ。駅前のファーストあるから、そこ来れる?」と返信が届いた。
アカリは少しだけ悩んでから、「行くね」とだけ送った。
──駅前のファーストフード店。
数週間前、そこで初めて会った女の子の顔が、ふと脳裏によぎった。
再会と気まずさのハンバーガー
駅前のファーストフード店に入ると、ハルキは奥の窓際席に座っていた。
「おつかれ〜」
アカリが声をかけると、ハルキが顔を上げて軽く手を挙げた。
「おつかれ。あ、これ、バイトのシュウ。覚えてる?」
「いるじゃん、シュウ。元気だった?」
「え、アカリじゃん。ひさしぶり〜!なんか雰囲気ちょっと変わった?」
「そっちこそ。てかふたりでごはん中だった?」
「ううん、たまたまハルキと上がり時間いっしょだったから、ダベってただけ」
アカリはちょっとホッとして、同時に少し胸がざわついた。
「あ、おみやげってこれ?」
ハルキが紙袋を受け取る。
「うん。江ノ島でイルカのキーホルダー見つけてさ。来れなかったし、雰囲気だけでもどうぞ」
「ありがと」
ハルキは照れくさそうに笑って、キーホルダーを取り出してじっと見た。
「めっちゃ可愛いじゃん。俺、イルカ好きって言ったっけ?」
「言ってない。けど、なんか合いそうだなって」
その場の空気が少しやわらいだ気がした。だけど、すぐにシュウが口を開いた。
「ねえ、アカリとハルキって、なんか付き合い長いよね?雰囲気ちょっと似てきてない?」
「え〜?どうかな、ふつーに仕事の話ばっかだよ。たまにバカな話もするけど」
「でも、そーゆー空気感、嫌いじゃないな〜」
軽いトーン。でも、アカリの中に何かがじんわり広がっていく。
──この子、ほんと自然に入り込んでくるな。
気づかない気持ちと、冷めかけのポテト
「じゃ、うちそろそろ行くね」
紙袋から手を離したあと、アカリはトレイのポテトに視線を落とした。いつの間にか冷えていて、さっきより味気なく感じる。
「え、もう?せっかくだし、もうちょい喋ろうよ」
シュウがあっけらかんとそう言う。無邪気な笑顔。悪気は、たぶんない。
「いや、家で課題やんなきゃで。あんまり遅くなれないんだ」
「そっか。真面目〜。ハルキとは違うタイプだね、ほんと」
「それ、たぶん褒めてないよね?」
軽口で返したけど、アカリの心はほんの少しだけ沈んでいた。
「ハルキ、またね。おみやげ、バッグとかにつけてくれたらうれしいかも」
「うん。ありがと。……気をつけて」
店を出ると、駅前の空気がやけに静かに感じた。
──シュウの隣にいるときのハルキって、けっこうしゃべるんだな。
──てか、なんでそんなこと気にしてるんだろ。
アカリは自分の中に芽生えたモヤモヤの正体がわからないまま、イヤホンを耳に差し込んだ。
プレイリストから、なんでもない恋の歌が流れはじめる。
ほんのちょっと、だけど確かに。
胸の奥が、きゅっと鳴った気がした。
気づくには、まだ少しだけ遠くて
帰り道、電車の窓に映る自分の顔をなんとなく見つめる。
「はぁ……なんか、よくわかんない」
手のひらを開くと、スマホの通知が光っていた。
ハルキからのメッセージ。
『キーホルダーありがとな。アカリらしくて、ちょっと笑った』
なにそれ、アカリらしいってどゆこと?
ツッコミたいけど、ちょっとニヤけてる自分がいて、イヤになる。
──好きとかじゃない。そんな特別な感情じゃない。
でも、なんでだろ。
帰りたくないって、ちょっとだけ思っちゃった。
窓の外には、夕暮れに溶けていく街の灯り。
気づけば、あたしのイヤホンから流れてるのはラブソングばっかりだった。