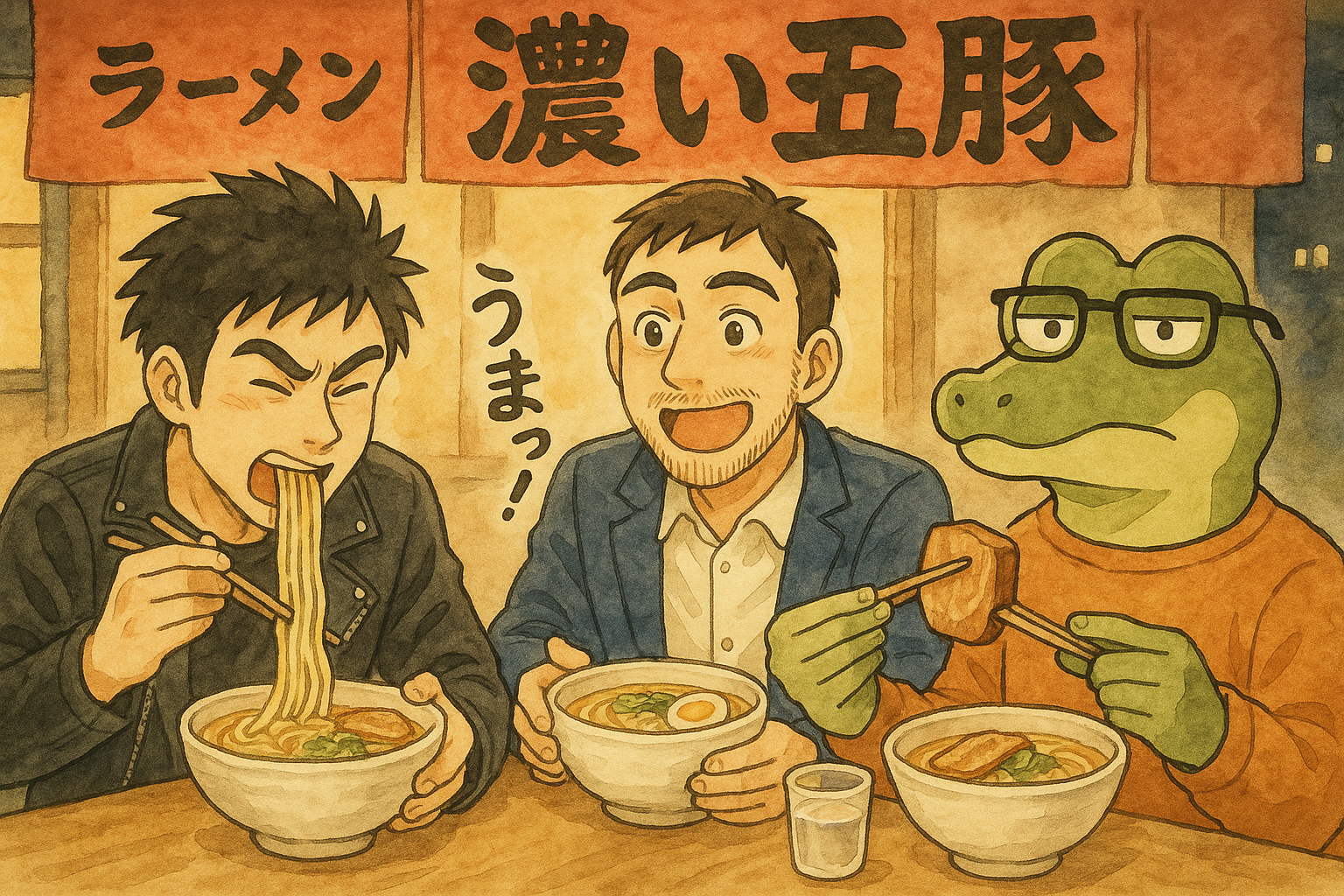ラーメン屋「濃い五豚」での夜
ケンジが「うまいラーメン屋があるから若いやつ連れてく」と言い出したのは金曜の夜だった。
向かった先は、編集部の近くにあるラーメン屋「濃い五豚(こいことん)」。
看板はちょっと色あせているけど、にんにくとスープの匂いが外まで漂って、すでに腹が鳴る。
ケンジの後ろを歩くのは、10代のハルキと、どこか冷静なワニオ。
「ここが俺の行きつけだ。ラーメンはな、恋愛と同じで、出会いが大事なんだ」
ケンジがいきなり説教モードに入ると、ハルキは「え、ラーメンで恋愛ですか?」と笑い、
ワニオは「麺とは縁と似ておりますね」と哲学的につぶやいた。
のれんをくぐってカウンターに座ると、湯気と炒め油の音が一気に押し寄せてくる。
「よし、若いやつに濃い味を教えてやる」と、ケンジは豪快にチャーシューメンを三つ注文した。
湯気の向こうで始まる男たちのトーク
ほどなくして、大きな丼に盛られたラーメンが運ばれてきた。
スープの表面には背脂が浮き、チャーシューがどんと構えている。
立ちのぼる湯気に、3人とも思わず「おぉ」と声をそろえた。
ケンジは箸を割ると同時に「ラーメンはな、待たせちゃいけねえ」と言って豪快にすすり始める。
ハルキは「うまっ!なんすかこれ、めっちゃパンチありますね」と目を輝かせ、
ワニオは麺を見つめて「この縮れは、人生の複雑さそのものですな」とつぶやいた。
「お前は相変わらず話がずれてんなぁ」とケンジが笑う。
「いやいや、ワニオさんっぽいっすよね」とハルキも笑いながら、豪快に麺をすすった。
ラーメンをすすりながら、ふとケンジがハルキに話を振る。
「そういやハルキ、お前ギター始めたんだってな?」
「あ、はい。実はケンジさんが編集部で流してた曲、あの重くて激しいてやつ。
あれ聴いて、やばいって思ったんです。ギターかき鳴らしたくなって」
ケンジの眉が少し上がる。
「おぉ、あれが刺さったのか。90年代のグランジだ。俺が若いころぶっ壊れるほど弾いてた音楽だよ」
ハルキは笑いながらスープを飲む。
「まじで、あのざらついた音に惹かれて。恋愛のこととかもうどうでもよくなるくらい、ギター弾きたくなって」
「おいおい、恋よりギターか?青いなぁ」ケンジはチャーシューをほおばりながら笑った。
ワニオはレンゲを持ったまま首をかしげる。
「恋愛より音楽。ふむ……効率的ではないですが、魂の燃焼としては理解できますね」
ハルキとギター、そして90年代の影響
「ギターって、ただ音鳴らすだけなのに、なんでこんなに熱くなるんすかね」
ハルキがそう言って、箸を置いた。丼の中のスープはまだ湯気を立てている。
「90年代ってのはな、どこか景気も気分もくすんでてよ、みんなモヤモヤ抱えてたんだ。
グランジはその鬱屈をぶちまけた音楽だった。
きれいごとのポップソング? そんなもんクソ食らえだ!みたいな感じでさ。
ギターは歪みっぱなしで、ドラムはドスドス重くて、陰気で荒っぽい。
だけどな、耳に残るメロディがあるんだよ。そこがまたズルい。
うまく生きられねぇ不器用さとか、やり場のない苦しさをそのまま叫んでてさ。
俺も若い頃は、まるで自分の心を代弁してくれているみたいで、思いっきり投影しちまったんだよな。」
ケンジは少し遠くを見るように語る。
「うん、あの音、めっちゃ響きました。
なんか“カッコよく見せたい”とかそういうんじゃなくて、“全部ぶちまけたい”って気持ちになったんすよ。
だから俺、初めてギター握ったとき、弾けなくてもコードじゃんじゃん鳴らしました」
ケンジは豪快に笑う。
「そうそう!下手でもいいんだよ。恋愛もギターも、形より中身だ。
心に響くかどうか、それがすべてなんだ」
ワニオはチャーシューを箸で持ち上げ、真顔でうなずく。
「なるほど。音楽とは“恋愛の代替物”ではなく、“恋愛と並ぶ表現形態”なのですな。
ただし、収益性と将来性の観点からは慎重な検討が必要ですが」
「いやいや!せっかく熱い話してるのに、ワニオさん現実的すぎっすよ」
ハルキが笑いながら突っ込むと、ケンジも腹を抱えて笑った。
「お前ら、ほんとキャラが正反対で面白ぇな」
![]()
男三人の恋バナは、ラーメンの湯気の中で
麺をすすり終えたころ、話題は自然と恋愛のことへ移っていった。
ケンジがレンゲを置き、ふと笑いながら言う。
「昔な、デートに金なんかなくてよ。ラーメン屋に女の子連れてきて、“俺の行きつけなんだ”って言ったことがある。
……今思えばダサいけど、当時は本気だったんだ」
ハルキが目を丸くする。
「ラーメン屋でデートっすか!?でもなんか、逆にアツいっすね」
ケンジはニヤリと笑う。
「アツいのはラーメンの湯気かもしれねぇけどな。
でも恋愛ってのは、場所じゃねえんだ。腹割って話せる空気があれば、それでいい」
ハルキは丼を抱え直しながら、力強くうなずいた。
「わかります!俺も、本気で好きになったら、デートの場所とか関係なく一緒にラーメンすすりたいっす」
ワニオはといえば、真顔でスープをすくいながら口を開く。
「しかし恋愛は、ラーメンほど安定供給されませんね。
スープの味は毎日変わらずとも、人の心は変わる。効率の悪い投資です」
ケンジとハルキが同時に「出た!」とツッコむ。
「いや、そういう考え方もあるけどさぁ!」とケンジが笑い飛ばし、
ハルキも「ワニオさん、それでよく編集部でやってけますね」と呆れながら笑った。
「恋愛は効率じゃなくて、勢いなんだよ」
「いや、恋は効率の悪さにこそ価値があるのかもしれません」
ラーメンの湯気の向こうで、そんな真逆の意見が飛び交った。
ラーメンの一杯に込められたもの
気づけば三人とも、丼を空にしていた。
テーブルの上には、汗をかいたグラスと、レンゲだけが残っている。
ケンジはタオルで口を拭いながら、しみじみと語った。
「なぁ、恋もラーメンも、こうして誰かと一緒に味わうからうまいんだよ。
一人で食うラーメンも悪くないけどな」
ハルキは力強くうなずく。
「やっぱり大事なのって、熱くなれることですよね。
ギターも恋もラーメンも、全部同じで、気持ちがこもってれば最高なんすよ!」
そしてワニオ。レンゲを丼に置いて、真面目な顔で言う。
「恋愛は複雑で、人の心は移ろいやすい。
しかし、このチャーシューは違います。
最後の一切れまで裏切らない。
──わたしにとっての“愛”は、このチャーシューでございますな」
ケンジとハルキが同時に吹き出す。
「おいおい、そっちかよ!」
「ワニオさん、やっぱ恋よりラーメンなんじゃないすか!」
笑い声と湯気に包まれながら、男三人の夜はゆるやかに更けていった。
「濃い五豚」のスープの香りが、なんだか友情まで濃くしてくれたような気がした。