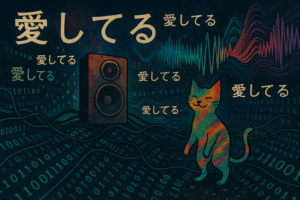鏡が恋を売る朝
朝霧がゆっくりとほどけると、街の奥で鐘が鳴った。音に導かれるように人々が歩き出す。目指す先は、今日も開かれる「恋の市場(マーケット)」──愛と見た目が等価交換される場所だ。
通りの両側には、背の高い鏡が並んでいる。鏡の裏では業者が慌ただしくライトを調整し、カメラを構え、鏡面を磨いている。鏡の中では、人々が化粧を直し、スーツのシワを伸ばし、眉の角度を確かめていた。
ここでは“恋のための支度”ではなく、“恋を売るための支度”が日課になっている。 眉の角度が1度違えば、ハート値が下がる。笑顔が0.3秒遅れれば、相場が動く。 誰もが、恋を投資のように扱う時代だ。
市場の中央にそびえる巨大な鏡は、恋価計(れんかけい)と呼ばれる。 人がその前に立つと、全身をレーザーのような光がなぞり、 肌・髪・姿勢・笑顔・香り・流行適合度──それらすべてを数値化して表示する。
上空に設置されたスクリーンに、金色の文字が踊った。
『ハート値ランキング:1位・光沢肌のカナ(92.7pt)/2位・涙袋リバウンドのマコト(88.3pt)/3位・無表情男子アツシ(86.4pt)』
拍手が広がる。羨望のまなざしが光を帯び、 誰もが自分の鏡に向かって、より整った顔を探す。
鏡の角度を少し変えると、笑顔が変わる。 微笑むたびに誰かの顔に似ていく。 ここでは“オリジナル”は価値を持たず、 “誰かっぽさ”が最高値で売れるのだ。
売り場の奥では、契約係たちが恋人契約書を束ねていた。 署名欄には「購入者」「被購入者」の二つの枠。 そして右下には、鮮やかな朱色のハンコ──返品不可。
そんな喧噪の中、虹色の毛並みをもつ猫──わたし、ナツメは市場の入口に立っていた。 誰よりも目立つはずの姿なのに、鏡の中には何も映らない。
「今日もよう映っとる。……せやけど、“映え”ってやつは恋の通貨になってもうたんやな」
通りの風が、鏡をかすかに揺らした。 そこに映るのは、無数の笑顔と、 ほんの少しの孤独だった。

映らない観察者と審査員ワニオ
わたし──ナツメは鏡の国で唯一、映らない存在だった。虹色の毛並みは光を撥ね返し、鏡面に映そうとすると静電気のようなノイズが走る。 そのせいで、わたしはこの市場の誰からも「存在しない」ことになっている。
それでも、毎朝ここに来てしまうのは、好奇心か、それとも習慣か。 光に群がる恋の形を眺めていると、胸の奥が少しザラつく。 愛が売られるたび、心のどこかで誰かの“値引き”が聞こえる気がするのだ。
そのとき、鈍い声がした。 「ナツメさん、今日の相場は上々ですな。」
振り向くと、緑色のスーツを着たワニが立っていた。 審査員証には『倫理部・特別監査官 ワニオ』と書かれている。 恋の市場のルールブックを監修する、皮肉と理屈の生きものだ。
「相場、ねぇ……。恋が株価みたいな言い方やな。」 「実際そうです。昨日の終値は“笑顔指数”の上昇で全面高。 一方で、“誠実さ指数”は微下落中。おそらく照明の影響でしょう。」
ワニオは淡々と語りながら、手元の端末にチャートを映す。 そこには赤と青の線が交差し、“トキメキ指数”“清潔感ボラティリティ”“初対面リターン率”などの見慣れない指標が踊っていた。
「……なあ、ワニオ。人はな、ほんまに“見た目”だけで恋するんか?」 「恋に中身を求める方が珍しいですよ。見た目が入口、興味がドア、中身は内装。 でもほとんどの客は、玄関で満足して帰るんです。」
ナツメは鼻で笑った。「そら、家具に恋してるようなもんやな。」 「そうとも言えます。ですが、家具は長く使えます。」 「……あんたの皮肉、磨きすぎて光っとるわ。」
ステージでは、オークションが始まった。 ピンクのライトが点滅し、司会者が叫ぶ。 「笑顔指数82からスタート! 一分で落札しないと、次の恋に乗り遅れます!」
会場の空気が熱を帯びる。 スマホ越しに配信される“リアル恋愛オークション”のコメント欄には、 「神顔すぎ」「推し確定」「沼った」と、光の文字が流れていった。
ワニオがぽつりと言った。 「この国では、“愛される”ことより“見られる”ことのほうが大事なんです。 だからみんな、鏡に恋してるんですよ。」
ナツメは尻尾で床を叩いた。 「せやけど、鏡はな、自分を好きになってくれることはないで。」
市場のどこかで、カシャッという音がした。 新しい恋が撮られた瞬間だった。
見た目で選ばれる恋/見えない恋の出品
午後になると、恋の市場はさらに熱気を帯びた。 スピーカーからは、どこか官能的なBGMが流れ、 司会者の声が恋のブローカーのように会場を煽る。
「はい、こちらの出品者、笑顔指数は82! 白い歯が素晴らしい! “第一印象がすべて”という言葉を体現したお方です! スタートはハート500から!」
観客たちはスマホを掲げ、電子ハートを連打した。 投げ銭のように愛情が飛び交う。 “恋”という名のデジタル通貨が、誰かの笑顔を一瞬だけ輝かせる。
その隣のブースで、ナツメは静かに屋台を開いていた。 看板にはこう書かれている。
『見えない恋、試飲可。』
ブースの上には、透明な瓶が並んでいた。 どの瓶にもラベルはなく、光を当てても何も映らない。 それでも、瓶の中ではなにかが微かに揺れている。 まるで、誰かの想いがまだ言葉になれずに震えているように。
最初にやって来たのは、派手な服の若い女性だった。 「なにこれ? 映えないね。SNSに載せられないじゃん。」 「映えへんけど、たぶん味はする。」 「味? なに味?」 「相手の寝癖を直すときの指のぬくもり。あと、夜中の既読スルーに泣いたあとに飲むミネラル味やな。」
彼女は笑ってスマホを構えたが、カメラには何も映らなかった。 「だめだ、バズらないやつだ。じゃ、またね。」 彼女の足音が遠ざかる。 鏡の前に並ぶ列のほうからは、再び拍手と歓声が起きた。
次に来たのは、背の高い青年。 白いシャツのボタンをひとつ開け、香水の匂いをまき散らしている。 「見た目で選ばれる恋しか勝たん。」 彼はそう言い、わたしの屋台を冷ややかに見下ろした。
「見た目で選べば外れない。中身なんて後から好きになればいいんだよ。」 「外箱で届いた期待はな、だいたい中身に返品されるで。」 「は? なにそれ。ポエム? 猫のくせに説教くさいな。」 「いや、ポエムやのうて“保証書”や。破れる前に読んどいたほうがええ。」
青年は鼻で笑い、恋価計のステージに向かった。 オークションの鐘が鳴り、落札額は史上最高値を記録。 群衆が立ち上がり、スマホの光が青年を包みこんだ。
だがその瞬間、恋価計が低くうなった。 デジタルの数字が一瞬だけ乱れ、鏡の表面に小さなヒビが入る。 司会者は笑って取り繕うが、ヒビは静かに広がっていく。 誰もその異変に気づかない。
ワニオが隣で呟いた。 「見た目の恋は高値で売れる。けれど、保管温度を間違えるとすぐ腐ります。」 「そらそうや。見た目は、恋の賞味期限の短さを隠すパッケージや。」 ナツメは尻尾で軽く地面を叩いた。 「せやけど、人は“中身”より“ラッピング”のほうを長く眺めとるんやな。」
ステージでは次の出品者が呼ばれていた。 「次は、“整った無関心”系男子! 目が合っても心が合わない奇跡の人!」 拍手が起きる。ナツメは小さく笑った。 「もはや恋ですらない。……でも、人はそれをロマンチックや言うんやな。」
鏡の崩壊と、映らない恋の残響
夕方、恋の市場が赤く染まり始めたころだった。 スピーカーのノイズが鳴り、司会者が戸惑いの声を上げた。
「おや……? 恋価計が、反応しません。測定不能……? そんなはずは――」
スクリーンの数字が一斉にゼロを示す。 ざわめき。群衆の視線が大鏡に集中する。 表面に浮かんでいた美しい顔が、ひとつ、またひとつと消えていく。
「……あたしの顔、映ってない!」「メイク、バグった!?」「誰か照明を戻して!」 パニックの声が飛び交う。 鏡は静かに、しかし確実に、ひび割れの音を立てていた。
やがて大鏡の中心が砕け、無数のガラス片が宙を舞った。 光が散り、群衆が息をのむ。 その光は虹のようであり、同時に、ひとりひとりの“本当の顔”を一瞬だけ映し出した。
――疲れた笑顔。 ――無理して上げた口角。 ――愛されたくて空っぽになった目。
鏡の破片の中で、ナツメは静かに立っていた。 「……鏡が割れても、恋の形は変わらんのやな。」
ワニオがその隣で腕を組んだ。 「ええ。けれど、みんな今ようやく気づいたでしょう。 “見た目”に恋していたと思っていたけど、 本当は“映っていた自分”に恋してたんですよ。」
ナツメはしっぽを一度だけ揺らした。 「それでもええ。 鏡が割れたあとに残るのは、映らへん恋や。 相手の顔が見えんくても、気づいたら好きになってる―― そんな恋、まだ売り切れてへんと思うで。」
市場に残ったガラス片たちが、風に吹かれて光る。 夜の灯りがそれらを拾い、街のどこかで反射する。 まるで、割れた鏡が空の星にリサイクルされたかのようだった。
ワニオが目を細めて言った。 「ナツメさん、あなた、鏡に映らないのに……なんでそんなに綺麗に見えるんです?」 「それはな、ワニオ。 映る努力やめたぶん、光る方向を間違えんようになっただけや。」
ふたりは歩き出す。 背後で、誰かがまだ鏡の破片を拾っている。 その手のひらには、ひとつの欠片が残っていた。 そこに映るのはもう顔ではなく、 小さな光――“見えない恋”の残響だった。
──そして翌朝。市場の掲示板には、新しい表示が現れた。
『恋価測定:無期限休止中。愛の価値は目視不能。』
ナツメは虹色の毛並みを風にそよがせ、 「せやろな」と小さく呟いた。 その声は、まるで欠けた鏡を撫でるように、優しく響いた。