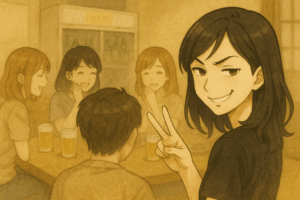チョロ助はまだ告白してこない
あの夜のこと──。
小さな折りたたみ傘の中で、ぬくもりを感じながら、リクと手を繋いだ。 その瞬間、わたしたちは“友達以上”の何かになったような気がした。 でも、それはあくまで私の中だけの話。
彼からの「好きだ」という言葉は、まだない。 そう、“告白”が、ないのだ。
正直、焦れてる。
いくら慎重派でも、もう少し空気を読むってことはできないのかしら。 わたしがどれだけ脈ありサインを出してきたと思ってるの。
デート中は目を見て笑ってみせるし、少し甘えた口調も使う。 自然なボディタッチもしたし、「リクって本当に優しいね」なんて褒め言葉だって惜しみなく使った。
正直、恋愛記事で紹介されてる“脈あり行動”なんて、もうコンプリートよ。 それでも踏み出してこないって、どういうことなの。
遠慮してる? わたしが美人すぎて近寄りがたい? 自分にはもったいないなんて思ってる?
……いや、あるかも。 リク、あのチョロ助、やけに自己評価低そうだし。
とにかく、そろそろ告白させないと。 このままダラダラと“いい感じ”だけ続けられても困るのよ。 私は“こいこと。”に近づくためにこの男を──リクを──選んだ。 チョロそうだったから。 でも、ここまで奥手だと、逆に難易度高いんじゃない?
……とはいえ、嫌いになれない。
笑うタイミングとか、歩幅を合わせてくれるところとか、何気ない一言に優しさが滲んでるのよね。
だからこそイライラするの。 この進まない関係に。
そしてついに、その夜が来た。
少し洒落たレストランに入って、向かい合わせに座るチョロ助。 手は膝の上で落ち着かず、会話もぎこちない。
──これは、来るわね。
わたしは内心でニヤリと笑った。
だけど──
わたしも、少しだけ緊張していたのかもしれない。
「ここ、昔よく来てたんだよね。ある人と」
そんなことを、ぽろっと言ってしまった。
言った瞬間、気まずい空気が流れる。
「あ、ごめん、変なこと言っちゃった」って慌てて笑ったけど、自分でも驚いた。 何やってるの、わたし。
“元カレ”の影をちらつかせるなんて、どんな地雷発言よ。
それでも、リクは優しく笑って「ううん、全然」って言ってくれた。
──チョロ助のくせに、そういうとこだけ妙に包容力あるのよね。
やっとの告白。合格よ
ディナーのあと、リクがそわそわしながら「夜景でも見に行こうか」と言ってきた。
──来たわね。
ベタな流れだけど、告白ってそういう“わかりやすさ”がちょうどいいのよ。 恋愛ライターなら、それくらい心得てるはず。
「うん、行こう」とにっこり返す。 でも……その夜景スポット、まさかの立ち入り禁止。まさかの工事中。
ええぇぇぇ〜!?
この期に及んで間の悪さを見せるチョロ助。もう、逆に芸なの?
「ごめん、なんか全部崩れた……」
焦ってる顔が、ちょっとかわいい。 でもここで萎えさせるわけにはいかないの。
私は落ち着いた声で言ってあげた。
「じゃあ、こっち歩いてみよう?」
夜の坂道を選んだのは、もちろん“そういう空気”を維持するため。
静かな並木道。人影も少なく、ふたりだけの空間みたい。 チャンスはここしかない。
わたしはそっと言ってみる。
「今日、すごく楽しかったよ」
「……そっか」
「ありがとう」
まるでこいこと。の記事に出てくる“告白させるための魔法のフレーズ”そのまま。 正直わたし自身が書いた気がするくらい使い古されたセリフだけど、 チョロ助には効くのよ。簡単に。
案の定、ポケットから手を出して、わたしの手にそっと触れてくる。
(はい、きた)
でも、わたしもドキドキしてるなんて……なんか、ズルいわ。
そして、次の瞬間。
「ミサキ」
「……うん?」
「好きです」
──ついに来た。チョロ助からのシンプルな告白。
「ずっと、伝えたかった。タイミング考えてたけど、全部飛んじゃって……」
……なんて素直で真面目なやつ。
可愛い、って思っちゃった。 思わず、わたしも手をぎゅっと握り返してた。
「私も……リクが好き」
言ったあと、恥ずかしくて顔が熱くなる。
……え、何? この感情。わたしらしくない。
チョロ助のくせに、ちょっとかっこいいじゃない。
街灯の下、リクが私をそっと抱き寄せた。 その腕の中で、私は一瞬だけ素直な“女の子”になってしまった。
──まあ、合格よ。
恋愛臆病と書いてリク。 でも今夜だけは、チョロ助でも、ちょっとヒーローに見えたわ。
恋人になったわたし、そして──本当の目的へ
やっと、手に入れた。
チョロ助ことリク──こいこと。編集部所属、恋活中、性格はお人好しでちょっと頼りないけど、女の扱いはやたら丁寧。
そんな彼と、ついに恋人になった。
同じ傘に入り、手を繋ぎ、告白されて、ハグされて……おまけに「好きです」なんて真っ直ぐすぎる言葉まで。あれはちょっとだけ、胸に来たわね。
でも――忘れないで。わたしの本当の目的は恋じゃない。
狙うのは、リクじゃなくて「こいこと。」。
リクの彼女になることは、こいこと。への第一ステップにすぎないの。ちゃんと計算づく。最初からそのつもりで近づいたんだもの。
今、私はその扉の前に立っている。
これからどうやって、その扉を蹴破って入ってやるか。作戦会議はわたしの頭の中で常に進行中。
たとえば、こんなプラン。
- リクを使って編集部メンバーに会わせてもらう。
- 座談会に「彼女として」ちゃっかり参加。
- ライターたちと仲良くなって、文才を認めさせてスルッと滑り込む。
そうやって、「チャンスを待つ女」から、「勝ち取る女」へと進化してきたのよ。
待ってるだけの女なんて、とっくに卒業したの。
……とはいえね。
恋人関係も、案外悪くない。
仕事終わりの「おつかれさま」LINE、休日のカフェ巡り、駅で待ち合わせて手を繋ぐ瞬間――
「チョロ助、今日のスイーツは私の好きなやつじゃない?……フフ、合格」
とか言いながら、ほんのちょっと頬が緩んだのは、内緒。
リクが、わたしを本気で大切にしようとしてるの、伝わってくるから。
でもこれは「こいこと。」に近づくためよ?恋に溺れて、本来の目的を忘れたら、それこそ本末転倒。
「まぁ、しばらくは恋人ごっこも楽しませてもらうわ。チョロ助、わたしを飽きさせないでね?」
そう。こいこと。に入ることも、恋人との甘い日々も、どっちも欲しい。
欲しがります、勝つまでは。
わたしは強欲な女。
強欲と書いて、ミサキと読むのよ。
コラムで勝負、わたしの文才を見せてあげる
恋人になって、手を繋いで、キスして、週末はおうちデート。
──ふふっ、順調じゃない。
いよいよ“作戦”は佳境へ。
リク、あなたが“こいこと。”に繋がるためのパイプであることは変わらないけど、恋人関係も悪くないわね。
花が好きだと言えばブーケを買ってきて、交際一カ月記念日にはスイーツを用意してくれるなんて。
まあ、ベタすぎて赤面ものだけど……女って、こういうのに弱いのよ。
「これ……好きなやつだよね?」
そう言って差し出されたケーキを受け取りながら、私は思わず口元をほころばせる。
仕方ないでしょ。チョロ助のくせに、たまに点を取るのよ。まったく、憎めないわ。
でもね。
私はこの恋に溺れるつもりはない。
“こいこと。”に近づく。それが最大目標。恋愛なんて、あくまで手段よ。
「ねぇ、ちょっとだけ、書いてみたの。文章」
そう言ってリクにノートパソコンを差し出したのは、ある意味“勝負”だった。
タイトルはつけなかったけど、中身はリクとの出会いから付き合うまでをまとめたもの。
あえて感情を淡々と描きながらも、所々に本音がにじむようにした。
これで「書ける女」アピールは完璧。うまくいけば、ライターの道も見えてくる。
「すごいね……」と、読みながらリクが息を漏らす。
よし、手応えあり。
「お世辞抜きで……ちゃんと文章になってる。下手したら、僕より上手いかも」
──はい、出ました♡
「ほんと? うれしい……。実はずっと、文章書くの好きだったんだ」
ここは演技よ、もちろん。でも、完全な嘘じゃない。
私は自分の言葉で、世界を動かしたい。ついでに編集部持ちで旅行にも行きたい。座談会と称してタダで飲み食いもしたい。フフフ。
そのために、“こいこと。”という舞台が必要なのよ。
「こいこと。のライターに向いてるかもしれないね」なんて言われて、
リクの中で、私は“書ける彼女”としての位置を獲得した。
次は、座談会参加よ。待ってなさいアカリちゃん♡
「……いつか、あのメディアで書けたらいいな」
そう呟くと、リクは優しい顔で頷いた。
さあ、チョロ助。
あなたの可愛い彼女を、“こいこと。”に紹介しなさいよ。
私はこいこと。のライターになる女。
こっそり整理整頓と書いて、愛のしるし♡
お家デート中のある午後。
リクがキッチンでアイスコーヒーを淹れている間、リビングの隅に積まれた紙類がふと目に入った。
書類や封筒がごちゃっと乱雑に置かれていて……うーん、生活感がすぎるわね。
「……ちょっと整えておいてあげようかしら」
軽い気持ちで、書類をそっとまとめて持ち上げたときだった。
──目に入った、薄い茶封筒。
封が甘く、しかも中身がなんとなく透けて見えた。
カラー写真? ……ツーショット。
え? なにこれ──
手が勝手に動いた。そっと封筒を引き出し、覗き込む。
そこには、リクと、知らない女の子が並んで笑って写っていた。
……つまり、元カノってやつ?
しかも、けっこう良い笑顔してるじゃない。チョロ助、やるわね。
「って、そうじゃないでしょ!」
わたしというものがいながら、まだこんな写真を残してるなんて。
どんな未練よ、まったく。
わたし、今ここにいるんですけど?
あの手つないだ夜も、告白された瞬間も、この間の手作りワンプレートランチも──全部、嘘なの?
いや、嘘じゃないでしょ。でも、でも……。
(……ああもう、面倒くさい女じゃないわよ、わたし)
こんなものなんで出してるの?たまたま資料と一緒に出ちゃった?とにかくわたしに対して無礼よ。
封筒をそっとカバンに滑り込ませる。
そして、帰り道の途中。
コンビニのゴミ箱の前で、わたしは一度、立ち止まった。
「写真の処分と書いて、恋のクリーニング♡」
そうつぶやいて、笑顔でゴミ箱に封筒を入れた。
……あら? ちょっと胸が痛いのは、気のせい?
フフフ、気のせいね。
だってこれは、恋のメンテナンスよ。こいこと。メンバーになるには、雑音は不要。
それに──
「ちょっとくらいヤキモチ焼く女のほうが、可愛いっていうじゃない?」
わたしってば、ほんとできた彼女♡
第4話へつづく